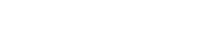TOP > 症例紹介
イヌの僧帽弁閉鎖不全症 2025.04.22
【病態】
僧帽弁閉鎖不全症は、心臓の左心房と左心室の間にある僧帽弁がうまく閉じなくなることで、血液が逆流し、心臓に負担がかかってしまう慢性的な心疾患です。特に小型犬や中高齢の犬に多く見られ、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルやチワワ、マルチーズなどの犬種で好発します。
病気が進行すると、左心房に血液がうっ滞し、肺に水がたまりやすくなる「肺水腫」を引き起こすこともあります。初期は無症状であることが多いですが、進行すると咳や呼吸困難、運動不耐性(すぐに疲れる)、失神などの症状が現れるようになります。
【診断】
診断には、身体検査での聴診が重要です。僧帽弁からの逆流による雑音が聞かれることが多く、これをきっかけに精密検査へと進みます。
心エコー検査では、僧帽弁の構造異常や逆流の程度、心臓の拡大具合などを確認します。心電図や胸部レントゲン検査も併用することで、心臓のリズムや肺の状態を評価することができます。最近では、心臓病の進行度を評価するために「NT-proBNP」という血液検査も活用されています。
この病気は進行性であるため、定期的な検査で病状の変化を把握することが非常に重要です。
【治療】
根本的に僧帽弁を治すことは難しいため、治療は主に内科的に行われます。逆流によって負担のかかった心臓の働きを助けるために、ACE阻害薬や強心薬、利尿薬が処方されます。肺水腫のリスクがある場合は、利尿薬を優先的に使用して呼吸を楽にします。
日常生活では、塩分を控えた心臓病用の療法食への切り替え、過度な運動の制限、ストレスの回避などが求められます。
病状が進行して内科治療だけではコントロールが難しい場合、一部の専門施設では外科的に僧帽弁を修復する手術が検討されることもありますが、現状では限られた施設でしか実施されていません。
【予後】
僧帽弁閉鎖不全症は進行性の病気ではありますが、早期に発見して内科的管理を行うことで、症状の進行を遅らせ、快適な生活を長く維持することが可能です。
適切な投薬と定期的な検査、生活管理を行うことで、数年以上にわたって元気に過ごしている犬も多くいます。
ただし、肺水腫を繰り返すようになると命に関わるリスクが高まりますので、呼吸状態の変化や咳の悪化には十分に注意が必要です。飼い主さんが日々の様子を観察し、異変に気づいた時点で早めに動物病院を受診することが、長期的な予後の改善につながります。