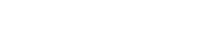TOP > 症例紹介
ウサギの下顎膿瘍 2025.04.25
【病態】
ウサギの下顎膿瘍は、主に歯の疾患や外傷などをきっかけとして発生する細菌性の感染症で、下顎の骨周囲に膿がたまる病気です。ウサギは歯が一生伸び続ける動物であり、不正咬合や歯根の異常があると、細菌感染の温床となりやすくなります。特に下顎の切歯や臼歯の歯根から感染が起こり、顎骨に炎症が波及して膿瘍が形成されるケースが多く見られます。
膿瘍は硬くしこりのように感じられ、進行すると痛みや食欲不振、よだれ、歯ぎしりなどの症状が現れます。また、膿瘍が進行して骨を侵すと「骨髄炎」を伴うこともあり、非常に治りにくく慢性化しやすい病気です。
【診断】
診断はまず視診と触診によって、下顎にしこりや腫れがないかを確認します。膿瘍は一般的に硬く、内部に粘稠性の膿がたまっているため、典型的な触感があります。口腔内をチェックし、歯の不正咬合や歯根部の異常がないかも観察します。
さらに、X線検査やCTスキャンを用いて、骨への浸潤の程度や、歯根病変、膿瘍の広がりを評価します。感染を起こしている部位から穿刺を行い、膿の細菌培養や感受性試験を行うことで、使用すべき抗生物質を選定することもあります。早期の診断によって、治療方針の選択肢が広がります。
【治療】
治療の基本は外科的な膿瘍の切開・掻爬(そうは)と、感染源となっている歯の抜歯や、感染部位の除去です。ウサギの膿瘍は被膜に包まれて硬く、単に膿を抜くだけでは再発しやすいため、外科的にしっかりと病巣を取り除く必要があります。
同時に、抗生物質の投与を行い、細菌の増殖を抑える治療も併用されます。また、治療後は再発防止のために患部の洗浄やドレナージ処置を定期的に行う必要があります。
【予後】
ウサギの下顎膿瘍は、慢性化しやすく再発も多いため、完治を目指すには時間と根気が必要です。早期に診断・治療が行われた場合や、原因歯を適切に抜歯できた場合には、比較的良好な経過をたどることがあります。しかし、顎の骨が大きく破壊されていたり、完全に病巣を除去できなかった場合には、再発を繰り返すことがあります。
そのため、定期的な口腔内チェックと、食事管理による不正咬合の予防が非常に重要です。特に繊維質の多い牧草中心の食事を心がけ、歯の自然な摩耗を促すことが膿瘍予防にもつながります。飼い主さんの早期の気づきと継続的なケアが、ウサギの健康を守る鍵となります。