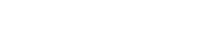TOP > 症例紹介
ウサギの腎不全 2025.10.18
【病態】
慢性腎不全は、腎臓の機能が長期にわたり低下し、老廃物や水分、電解質の調整ができなくなる疾患です。腎臓の糸球体や尿細管の構造的な破壊が進行し、不可逆的な機能障害を引き起こします。
原因はさまざまで、細菌性腎盂腎炎、尿路結石による閉塞、脱水や中毒、長期的な高カルシウム血症などが関与します。特にウサギはカルシウム代謝が特殊で、摂取したカルシウムの大部分を腎臓から排泄するため、高カルシウム尿症に起因する腎障害が比較的多くみられます。
腎機能の低下により、体内に尿素窒素やクレアチニンが蓄積し、代謝性アシドーシスや電解質異常を引き起こします。臨床的には多飲多尿、体重減少、被毛の粗剛化、元気消失、食欲不振、尿量減少などがみられ、進行すると尿毒症症状を呈するようになります。
【診断】
診断は、血液検査・尿検査・画像診断を組み合わせて行います。
血液検査では、BUN・CREの上昇、リン濃度の上昇、ナトリウムやカリウムの異常が確認されることが多く、腎機能障害の指標となります。また、貧血がみられることも特徴です。
尿検査では低比重尿(尿が薄い)や蛋白尿がみられ、尿沈渣で細菌や結晶が確認される場合もあります。
画像診断として腹部X線検査や超音波検査を実施し、腎臓の大きさ、形態、結石の有無、腎盂拡張などを評価します。慢性経過では腎臓が縮小し、皮髄境界が不明瞭になる所見がみられることがあります。
また、急性腎障害との鑑別のために、過去の臨床経過(症状の進行速度)や既往歴(尿路疾患の有無)を確認することも重要です。
【治療】
慢性腎不全の治療は根治が難しく、進行抑制と症状の緩和が主な目的となります。
脱水の改善と尿毒素の希釈を目的として、皮下または静脈から輸液を行います。また食欲増進剤、制吐剤、リン吸着剤、胃腸保護剤、ビタミンB群などを症状に応じて使用します。二次性高血圧がある場合は、ACE阻害薬を併用することもあります。さらに細菌感染を伴う場合には、腎毒性の少ない抗菌薬を慎重に選択して投与します。
慢性的な腎機能低下により電解質バランスが不安定なため、定期的な血液検査によるモニタリングが不可欠です。
【予後】
ウサギの慢性腎不全は、早期発見と支持療法によってある程度の生活の質を保つことが可能ですが、進行した症例では回復が難しく、数か月から1年程度で再び症状が悪化することが多いです。
治療により一時的に食欲や活動性が改善しても、腎組織の再生はほとんど期待できません。したがって、食事管理・水分摂取の維持・環境ストレスの軽減が予後改善の鍵となります。
特に高齢ウサギでは腎疾患の発生率が高いため、年1~2回の血液・尿検査によるスクリーニングが推奨されます。
« 前の記事