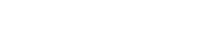TOP > 症例紹介
トリの卵巣・卵管腫瘍 2025.10.18
【病態】
鳥類の卵巣・卵管腫瘍は、特にセキセイインコ、オカメインコ、文鳥などの小型鳥類に多く認められる生殖器系疾患です。腫瘍は卵巣(卵胞由来)または卵管上皮から発生し、良性・悪性いずれの病変もみられますが、臨床的には腺癌(卵管腺癌)の報告が多く、悪性腫瘍として進行する例が少なくありません。
発症には、長期間の排卵刺激や慢性的なホルモン異常が関与すると考えられています。特に年齢の高い未繁殖メスや長期間発情状態が続いている個体では発症リスクが上昇します。
腫瘍が増大すると、腹部膨満、体重増加、腹水貯留、呼吸困難、飛翔困難、排便障害などを引き起こし、進行すると腹腔内出血や転移による全身症状を呈します。
また、腫瘍から分泌されるホルモンの影響で、偽卵産生や発情行動の持続を伴うこともあります。
【診断】
診断は、視診・触診・画像検査・血液検査を組み合わせて行います。
まず、臨床的には腹部の膨隆や呼吸状態の変化を確認します。腫瘍性腹水がある場合には、腹部が柔らかく膨らみ、体重が増加していることが多いです。
X線検査では、腫瘤状陰影や腹腔内の不透過性上昇、卵殻形成異常などが確認されることがあります。さらに超音波検査では、腫瘍の内部構造(嚢胞性・充実性)や、周囲臓器との位置関係を把握することが可能です。
血液検査では、貧血、白血球増多、肝酵素上昇(特にAST、LDH)などがみられることがあります。また、卵巣・卵管腫瘍の一部では女性ホルモン値の上昇が検出されることがあります。
最終診断は、摘出組織の病理組織学的検査により行われ、良性腫瘍か悪性腫瘍かの判定がなされます。
【治療】
治療の第一選択は外科的摘出(卵巣・卵管切除術)です。
ただし、鳥類の生殖器は解剖学的に複雑で、腫瘍が大血管や腎臓・消化管と密接しているため、全摘出が困難な場合もあります。そのため、手術のリスクを慎重に評価し、全身状態の安定化と麻酔リスク管理が重要となります。
腫瘍が進行しており手術適応がない場合、ホルモン療法を用いて発情抑制やホルモン依存性腫瘍の縮小を試みることがあります。
また、腹水除去・利尿剤投与・栄養管理・酸素療法などの支持療法も併用されます。悪性例では再発率が高く、対症療法中心の長期管理が必要になることもあります。
【予後】
予後は腫瘍の種類と進行度によって大きく異なります。良性の卵巣嚢腫や限局性腺腫では外科的切除により良好な経過をたどることが多い一方、卵管腺癌や転移性腫瘍では再発率が高く、数か月以内に再び腹水が貯留するケースもあります。
早期発見と治療によって生活の質を維持できることもありますが、悪性腫瘍の長期生存率は低く、平均生存期間は6か月前後とされています。
発情抑制(照明管理・体重管理・ホルモン療法)を行うことで、再発や新たな腫瘍発生のリスクを下げることができます。定期的な腹部エコー検査とホルモン値モニタリングが、早期発見に有効です。