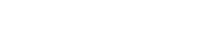TOP > 症例紹介
トリの腺胃拡張症 2025.10.18
【病態】
腺胃拡張症は、主にオウム目やインコ目に見られる神経性の疾患で、ボルナウイルス(Avian Bornavirus:ABV)の感染が原因とされています。感染によって神経系、とくに消化管の運動を司る神経が障害されることで、腺胃や筋胃、さらには全腸管の蠕動が低下します。その結果、腺胃が異常に拡張し、食べたものがうまく消化・通過できなくなります。
主な症状は、食欲があるにもかかわらず体重が減る、未消化の餌を吐き戻す、便中に種子がそのまま含まれる、排便量が減るなどです。また、神経症状(ふらつき、脚の麻痺、けいれんなど)を伴うこともあり、病変が中枢神経に及ぶと運動障害や異常行動がみられる場合もあります。発症は慢性的に進行することが多く、飼い主が気づいたときにはすでに重度の腺胃拡張を呈していることがあります。
【診断】
診断は、症状と画像検査、そしてウイルス検査の結果を総合して行います。X線検査では、腺胃が著しく拡張し、体腔内で長いチューブ状の陰影として確認されることが多いです。さらに造影X線検査を行うと、消化管の通過遅延や胃内容物の停滞が明確にわかります。超音波検査では腺胃の拡張や壁の菲薄化が確認でき、他の消化管疾患との鑑別にも有用です。
また、ボルナウイルス感染の有無を確認するために、糞便や羽、血液を用いたPCR検査が行われます。陽性であればPDDが強く疑われますが、陰性でも感染を完全に否定できないため、臨床症状との併用判断が必要です。確定診断には腺胃や脳の組織病理検査での神経炎の確認が求められますが、生前に行うのは困難なことが多いです。
【治療】
現時点で、ボルナウイルス感染自体を根本的に治す治療法は確立されていません。そのため、治療の目的は症状を軽減し、できるだけ快適に過ごさせる支持療法が中心となります。消化器症状が強い場合には、消化のよい食事を少量ずつ頻回に与え、嘔吐や便秘を防ぐことが大切です。脱水がみられる場合には輸液療法を行い、必要に応じて抗炎症薬や免疫抑制薬が使われることもあります。
また、ストレスや温度変化が症状を悪化させる要因となるため、静かで一定した環境での飼育が推奨されます。発作や神経症状を伴う場合には、鎮静剤や抗けいれん薬を使用して症状の緩和を図ります。感染の拡大を防ぐため、同居鳥がいる場合には隔離が必要です。
【予後】
腺胃拡張症は慢性的に進行する難治性の疾患であり、予後は一般的に不良です。治療によって一時的に症状が軽減することはありますが、根本的な治癒は期待できません。発症から数か月で衰弱死に至る例も多く、長期生存できるケースは限られています。ただし、早期に支持療法を開始し、栄養管理と環境調整を徹底することで、ある程度の生活の質を維持できる場合もあります。
予防のためには、新しく導入する鳥に対してボルナウイルスの検査を行い、感染個体との接触を避けることが最も重要です。定期的な健康チェックと早期の異常発見が、進行を遅らせるための鍵となります。