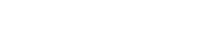TOP > 症例紹介
フクロモモンガの根尖膿瘍 2025.10.18
【病態】
フクロモモンガの根尖膿瘍は、歯の根元(歯根部)で細菌感染が起こり、膿がたまる病気で、慢性的な歯根炎が進行して膿瘍形成に至ります。原因としては、不適切な食餌による歯の過伸長、外傷、口腔内感染、免疫力の低下などが挙げられます。
膿がたまることで、顔の腫脹や歯のぐらつき、流涙、鼻汁、食欲不振などの症状が現れます。膿瘍が顎骨や鼻腔、眼窩に広がると、痛みや変形が進行し、重症化することがあります。フクロモモンガは夜行性で警戒心が強いため、食欲の低下や毛づやの悪化など、初期の変化を見逃さないことが重要です。
【診断】
診断は、身体検査と視診・触診により顔や口周囲の腫脹の有無を確認することから始まります。口腔内の観察で歯の過伸長、欠損、膿の排出口(瘻管)などを確認しますが、フクロモモンガは非常に小さく、口腔内の観察が困難なため、麻酔下での精密検査が必要となる場合があります。
X線検査や口腔内視診によって、歯根部の感染範囲や骨の融解・変形の程度を評価します。膿の一部を採取し、細菌培養検査および感受性試験を行うことで、効果的な抗菌薬を選択することができます。
【治療】
治療の基本は、感染源となっている歯根および膿瘍の除去です。外科的に膿瘍を開放して排膿し、膿や壊死組織を徹底的に除去します。感染歯が原因の場合は、抜歯を行うことが根本治療につながります。
手術後は、抗菌薬の投与を行い、感染の再発を防ぎます。膿瘍腔内には洗浄やドレナージ処置を継続し、治癒を促進します。また、疼痛管理や栄養サポートも重要です。
【予後】
根尖膿瘍は早期に適切な処置を行えば治癒が見込めますが、感染が骨や鼻腔にまで広がっている場合は再発のリスクが高く、予後はやや慎重になります。慢性化すると再発を繰り返すことがあり、そのたびに外科的処置や抗菌療法が必要になることもあります。
また、食欲低下が続くと栄養失調や免疫力低下を招き、他の疾患を併発する危険があります。定期的な口腔チェックと、バランスの取れた食事内容の見直しが再発防止に役立ちます。