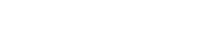TOP > 症例紹介
ヘビの呼吸器疾患 2025.05.17
【病態】
ヘビにおける呼吸器疾患は、細菌感染、ウイルス感染、真菌感染、寄生虫感染、飼育環境の不備など、さまざまな原因で発生します。最も一般的なものは細菌性肺炎で、これは温度・湿度の不適切な管理や、ストレス、免疫低下などが引き金となって発症します。
また、アデノウイルスやパラミクソウイルスなどのウイルス、アスペルギルス属などによる真菌感染、あるいは気管に寄生する線虫なども、呼吸器症状を引き起こす原因となります。飼育下では、複数の病因が同時に関与することも珍しくありません。
病態としては、肺や気管支への炎症、粘液の貯留、気道閉塞などが進行し、呼吸困難や二次感染を引き起こすことがあります。ヘビは肺が1本、または退化した片方の肺しか持たない種も多いため、肺機能に対する影響は他の動物よりも深刻になりやすいです。
【診断】
診断は、まず臨床症状の観察から始まります。呼吸器疾患を患ったヘビは、口を開けて呼吸する(開口呼吸)、口腔内に泡状の分泌物が見られる、喘鳴、沈鬱や食欲不振などの症状を示します。
診断を確定するには、喉頭や気管内からの粘液サンプルを採取しての細菌培養検査や、レントゲン検査・CT検査による肺の評価が有効です。病原体の特定には、PCR検査や血清学的検査が必要になることもあります。鑑別すべき疾患には、口内炎や誤嚥、寄生虫感染による気管炎なども含まれます。
【治療】
治療は原因に応じて行いますが、広域スペクトルの抗菌薬の投与がまず基本となり、注射や経口で用いられます。ウイルス性疾患に対する特異的な治療法は少ないため、対症療法と環境改善、二次感染の予防が中心となります。
真菌感染に対しては、イトラコナゾールやボリコナゾールなどの抗真菌薬を長期間使用する必要があります。重度の症例では、ネブライザーを用いて、薬剤を直接気道に作用させる方法が効果的です。
また、飼育環境の改善も重要で、温度と湿度を適正に保つこと、清潔な床材への交換、通気性の確保などが求められます。適正温度と湿度は腫によって異なりPOTZと呼ばれる快適域におくことが大切です。
【予後】
予後は、発見の早さ、原因の特定、適切な治療の実施に大きく左右されます。軽度の細菌性肺炎であれば治療により回復する可能性が高いですが、慢性化や重度の気道閉塞、ウイルス感染症が関与している場合は、予後が不良となることもあります。
特に、免疫力が低下している個体や幼体、高齢個体では重症化しやすく、長期管理や繰り返す治療が必要になることもあります。再発を防ぐためには、適正な環境維持とストレスの軽減が重要であり、定期的な健康チェックが推奨されます。