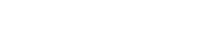TOP > 症例紹介
小型げっ歯類の歯科疾患 2025.05.17
【病態】
ウサギ以外の小型げっ歯類も、常生歯を持つ動物が多く、特にモルモットやチンチラでは、歯の不正咬合や歯牙過長による疾患がしばしばみられます。これに対し、ハムスターやラットの奥歯は常生歯ではありませんが、切歯は生涯伸び続けるため、咬合異常が生じると歯牙過長、歯折、口腔損傷などを引き起こします。
これらの齧歯類は、栄養バランスの偏った食事や咀嚼不足、外傷、遺伝的要因などによって歯列が乱れ、歯が過剰に伸びる、咬み合わなくなる、あるいは口腔内を傷つけるといった問題が発生します。奥歯の不正咬合があると舌や頬を圧迫し、よだれ、食欲不振、体重減少、毛づやの悪化などの全身症状が現れます。特にチンチラやモルモットは臼歯も常生歯であるため、臼歯の過長や根尖膿瘍などが深刻な問題となることがあります。
【診断】
診断は、食欲不振、体重減少、選り好み食い、流涎などの症状から歯科疾患が疑われます。口腔内の直接観察に加えて、器具を用いて切歯や臼歯の状態を確認します。ただし、奥歯の病変は視診だけでは分かりにくいため、全身麻酔下での口腔内検査が必要な場合もあります。
また、歯根や顎骨の評価にはX線検査が有用で、側面像や頭部の斜位撮影、CT検査によって、歯根膿瘍や骨変形、骨融解などを確認することができます。特にチンチラやモルモットでは、臼歯の根尖が眼窩や下顎神経に近接しているため、詳細な画像評価が重要です。
【治療】
治療の基本は、過長歯の切削・整復と基礎疾患や生活環境の見直しです。過長した切歯や臼歯は、専用の歯科ドリルやバーを用いてトリミングします。無麻酔での切歯切断はリスクが高いため、可能な限り全身麻酔下での処置が推奨されます。
チンチラやモルモットでは、臼歯の根尖が化膿して膿瘍を形成することがあり、この場合は切開排膿、抜歯、抗菌薬の投与などの積極的な治療が求められます。また食事内容の見直しも必要です。
ハムスターやラットでは、切歯の整復が比較的簡便である一方で、臼歯疾患はまれであり、主に切歯の咬合異常を管理することが中心になります。
【予後】
予後は動物種や病変の程度、飼育環境、治療のタイミングにより大きく異なります。早期に対応できた場合は良好な予後が得られることも多いですが、根尖膿瘍や顎骨変形、栄養不良が進行している場合には長期的な管理や定期的な処置が必要になります。
モルモットやチンチラでは、臼歯の管理を怠ると再発を繰り返しやすく、一生涯にわたっての歯科管理が必要になるケースもあります。定期的な体重測定や咀嚼行動の観察、口腔内のチェックを通じて、早期発見・早期対応が予後を大きく左右するため、飼育者への指導も非常に重要です。