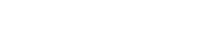TOP > 症例紹介
ネコの口腔内腫瘍 2025.05.17
【病態】
猫の口腔内腫瘍は、口の中に発生する腫瘍性疾患で、特に中高齢の猫で多く認められます。発生部位は歯肉、舌、口蓋、顎骨など多岐にわたり、進行することで食欲不振、よだれ、口臭、出血、顔面の腫れなどの症状を引き起こします。進行すると食事が困難になるだけでなく、顔面の変形や顎の骨の破壊など重篤な影響を及ぼします。
猫における口腔内腫瘍で最も多いのは扁平上皮癌です。これは特に下顎の歯肉に発生しやすく、局所浸潤性が非常に強いのが特徴です。その他にも、線維肉腫や悪性黒色腫などが発生することがありますが、発生頻度は扁平上皮癌に比べて低いとされています。いずれの腫瘍も、早期には炎症や歯周病と区別がつきにくいため、見過ごされがちです。
【診断】
診断にはまず視診と触診を行い、口腔内に明らかな腫瘤や潰瘍、出血、歯の動揺などが認められる場合には、腫瘍を疑います。ただし、炎症性疾患との鑑別が困難なことが多いため、確定診断には細胞診や組織生検が不可欠です。
画像診断も重要で、X線検査やCT検査によって顎骨の破壊の有無や腫瘍の広がりを評価します。また、肺などへの転移を評価するための胸部X線検査や、進行例では超音波による腹部検査も併用することがあります。病理検査の結果により、腫瘍の種類と悪性度を判定し、治療方針を決定します。
【治療】
治療の中心は外科的切除ですが、扁平上皮癌は顎骨に深く浸潤するため、完全切除を目指すには顎の部分切除など広範な手術が必要になることがあります。このような手術は術後の生活の質に影響を与えるため、十分な相談と理解が必要です。
完全切除が困難な場合や再発のリスクが高い場合には、放射線治療や化学療法が補助的に用いられることもありますが、猫の口腔内扁平上皮癌においては放射線や化学療法単独での効果は限定的であることが多いです。疼痛や感染の管理、栄養管理などの緩和ケアも非常に重要で、QOLの維持を重視した対症療法を選択することもあります。
【予後】
猫の口腔内腫瘍の予後は、腫瘍の種類や発見時の進行度、治療の可否に大きく左右されます。特に扁平上皮癌は早期に骨へ浸潤し、完全切除が難しいことが多いため、予後は一般に不良とされています。平均的な生存期間は数か月程度であることも少なくありません。また胃ろうチューブが生涯必要になる場合もあります。
一方で、腫瘍が比較的早期に発見され、積極的な外科治療が成功した場合には、数か月から1年以上の延命が可能な場合もあります。定期的な口腔内のチェックや、軽微な異常の早期受診が、予後の改善につながる重要なポイントとなります。