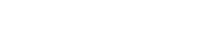TOP > 症例紹介
イヌの糖尿病 2025.10.17
【病態】
犬の糖尿病は、膵臓で分泌されるインスリンの不足、またはインスリンの作用低下により血糖値が慢性的に高くなる内分泌疾患です。多くは「インスリン依存型糖尿病(IDDM)」であり、膵臓のβ細胞が破壊されることでインスリンが十分に分泌されなくなります。好発年齢は中高齢(7〜9歳前後)で、特にメスや避妊手術を受けていない個体に多く、ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードル、柴犬などが発症しやすい傾向があります。肥満、ホルモン疾患(クッシング症候群、発情周期に伴うホルモン変動)も発症に関与します。
【診断】
代表的な症状は、多飲・多尿・多食・体重減少です。尿検査で糖が検出され、血液検査で空腹時血糖値が高値(200 mg/dL以上)を示す場合、糖尿病が疑われます。さらに、フルクトサミン値の上昇により、慢性的な高血糖状態を確認できます。合併症として肝酵素上昇、白内障、尿路感染症、ケトン体の出現などが見られることがあり、これらを総合的に評価して診断します。
【治療】
治療の中心はインスリン注射による血糖コントロールです。犬では経口血糖降下薬は効果が乏しく、1日1〜2回の皮下注射が一般的です。個体ごとにインスリンの種類と投与量を調整し、血糖曲線を作成して適正範囲内に維持します。あわせて食事療法も重要で、食物繊維を多く含み、糖吸収を緩やかにする療法食(高繊維・中等度脂肪食)が推奨されます。肥満犬では体重管理が不可欠です。また、避妊手術を行うことでホルモンによるインスリン抵抗性を減らすことができます。
【予後】
適切にインスリン治療が行われれば、良好な生活の質を長期間維持できます。しかし、管理が不十分な場合やケトアシドーシスを併発した場合には、急激な体調悪化を起こすことがあります。特に初期治療期は血糖値の変動が大きく、低血糖発作のリスクもあるため、獣医師の指導のもと慎重なモニタリングが必要です。長期的には白内障や尿路感染症、肝障害などの合併症に注意しながら、定期的な血液・尿検査を続けることで、安定したコントロールが可能となります